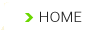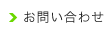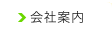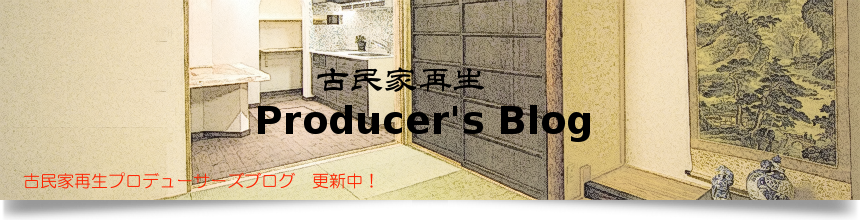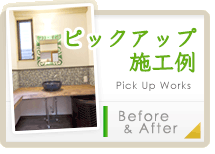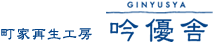『 最近の記事 』
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
建築こぼれ話 その2
「古家の土壁からは虫が出るの?」
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
今回の物件にも土壁がありましたが、別件で、
「しっくい壁の割れ目の土から虫が出てくるのでは?」
と、友人に相談されたことがあります。
結論から申しますと、虫はまずあり得ません。
壁自体が無くなるほど割れていなければ。
日本でのしっくい壁とは、壁の表面仕上げであり、
屋内で歩く時の振動でヒビが入りやすい下側の角が、
よく三角形に割れます。
また、古いしっくい壁が自然にはがれ落ちてしまい、
内部の土壁がむき出しになることもあります。
しっくい壁の寿命は、次の日〜百年以上まで、
塗った人間の腕次第だそうです。
プロの左官職人の目安は約10〜30年位でしょうか。
さて、内部の土壁の土ですが、じつは…
「現代の家造りに土壁が採用されにくいのは、時間を省くためだ」
と言う職人もいるほど、大変な手間がかかっているのです。
家一軒分の土を、建てる前に準備したという、
昔のやり方をざっくり説明いたします。
まず、土を、編み目の細かいザルでこしてサラサラにします。
大量の水と刻んだ稲ワラを加えて混ぜ、水がヒタヒタのまま
容器か掘っておいた穴に貯めてフタをして寝かせます。
半年〜1年後、ワラが腐って繊維になるころ、水加減を調節して
クワやシャベルで丁寧に練り上げ、やわらかい粘土状にしてから
竹を編んで作った壁芯(竹小舞:たけこまい)に塗り重ねます。
「鉄筋コンクリート」ならぬ「竹筋土壁」であり、
竹を芯にすると壁の強さが驚くほどアップします。
土は、水攻めの後、練り上げ工程ですり潰され、乾燥すれば
岩のように固くなりますから、虫は近づけません。
土壁は土に見えますが、製法を見ればむしろレンガや
コンクリートに近いと言えます。
地面にある土と、土壁との違い。
「レンガやコンクリートから虫が出てきますか?」
これが、答えの代わりになると思います。
おつきあいいただき、ありがとうございました!
Blogged by 小川 還
2013年5月5日 10:17 PM |
カテゴリー:2013年5月5日 |
コメント(0)
【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】
続報です。岩倉に建つ、洋館造りの古民家についてお伝えします。
(※以前のブログはコチラ → VOL.1・.2 )
駅を出れば鳥のさえずりが響き、見上げれば青い空に比叡山がそびえ、
周囲は、思わず住みたくなるような、お庭のある2階建ての住宅街。
お子様のいらっしゃるご家族様に人気の地域です。

遊具もある、近所の公園にて
さて、穏やかな住宅街の一角にある現場へまいりましょう。

(before)修復中でも、築約40年の風格あり

(before)懐かしい雰囲気のある窓やひさし
時間をかけて手入れされ、造り上げられた、優しい雰囲気の家です。
以前の住まい手のお人柄が偲ばれます。

(before)戸口(元 勝手口)より邸内をのぞく
勝手口のドアから、改築中の邸内へお邪魔しますと、

(before)庭へ面した大窓。右奥は増築部分
室内のむこうには、鮮やかな新緑のお庭が広がっていました。
家の右半分は増築中のリビングスペースで、庭へぐっと突き出ています。
左半分は、窓の外〜庭木の手前までウッドデッキになる計画です。
庭は、「庭園」といった堅苦しいスタイルではなく、
過去の住まい手がお気に入りの木を少しずつ植えられたようで、
草木が共生しひとつに溶け合った魅力的な「林の庭」です。
囲われた小さな畑もあり、遊んだり畑仕事を体験したりと、
子ども達に楽しみの多い空間となることでしょう。

(before)大窓前より左側。約40年ぶりの光をあびる土壁

(before)大窓前より右側。秋の紅葉も楽しめそうな増築部分

(before)増築部分(=リビングになる予定)から見た庭
床に置かれていた、入口から窓まで届くほど長くて太い木材は、
対面スタイルのキッチンを置くために引き抜いて撤去された
4本の柱に代わり、梁となって2階の柱をささえます。

(before)2階をささえる新しい梁(はり:柱と柱を結ぶ横の部材)
柱4本分の力に耐えるには、これぐらいの太さが必要です。
キッチンは庭向きに設置されますので、調理しながら子ども達が遊んでいる
リビングと庭とウッドデッキが一望できます。
賑やかな声が響き、一家でいらっしゃったお施主様は、
幼い3人のお子様がいらっしゃる若いご夫婦でした。
現場の職人さん達も目を細める可愛らしさで、元気いっぱい!
床工事中の1階は、遊べる場所も少ないので、近所の公園へ。
すると、よそのおうちからも小さな子どもがのぞいていました。
そんな訳で、公園の子どもたちから皆様へプレゼントです。

Please blow a fairy clock! (*^o^*)
幼い子は、綿毛をふうぅっとやるたび、なぜか笑顔になるみたいです。
そんな風に、住めばワクワクする和洋館を目指し、設計者と職人が
ドキドキしながら腕をふるっております。お楽しみに。
おつきあいいただき、ありがとうございました。
Blogged by 小川 還
10:16 PM |
カテゴリー:洋館造りの古民家 VOL.3 |
コメント(0)
【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】
『岩倉洋館造りの古民家』へリノベーション
解体工事をお伝えします!!
築40年程度と弊社の工事としては、まだ新しいほうの家だけあって、基礎や土台、梁は比較的しっかりしています。
計画の間取りに合わせて解体を進めていきます。
解体しなければ分からないことが多くあります。
岩倉のこの家は、外見から判断していた通り、欠陥(けっかん)もなく、しっかりした造りでした。
間取り変更に合わせて抜かなくてはならない柱が複数本あります。
抜いた後は、補強工事が必ず必要です。
この補強工事の仕方と位置は、施工する工務店任せということになります。
多くの場合、補強をしなくても直ぐに倒壊するということはありません。
しかしながら、施工者の判断ミスや経験不足、あるいは手抜きからこの補強工事を適当に終わらせることがあることも、また事実です。
弊社の場合は、施工管理をしている私自身が最終判断をしています。
もしもの時の責任は全て、最終責任者である私にあります。
この部分に関して、設計者や施工者(この場合は大工)に100%任せることはありません。
この部分で設計者や施工者(職人)と意見が食い違うことがありますが、私自身が納得できるまで補強工事を行います。
さて、前面道路側の生垣が撤去され、建物の全体の姿が現れました。
今度はこの位置に駐車場を計画しています。
南面のガーデンスペースの建具と壁が取り払われ、南からの太陽の光が燦々(さんさん)と内部に降り注いでいます。
南側にリビングゾーンを増築して、大型のサッシ窓を3箇所設置します。
工事の進行がとても楽しみです!!
Blogged by 松山 一磨(いつま)

前面道路側の生垣の撤去工事

こんなトラックで解体作業をしています!!

前面道路生垣撤去完了です!! 『やれやれ』のひと時・・・

玄関からまっすぐに有った内壁を撤去して柱がむき出しになった状態です。 間取りに合わせて手前の4本の柱は、抜かなければなりません!!
下の写真、向こうに見えるのが、南側ガーデンスペース。
この古民家の最も良いところの一つは、このガーデンスペースです。
ここにリビングスペースが突き出るスタイルで増築します。 いわば緑をいっぱいに感じられるリビングです!!
この太陽の光を最大限に取り込むために大型のサッシ窓を3箇所配置します。

対面キッチン設置予定の位置から南側の庭を臨んだ様子

この柱が4本並ぶところに対面スタイルのキッチンが配置される計画です。

大きな梁が2階の床を支えています。

南面庭園外部からの映像です。

この続きに大きな木製ウッドデッキを造る計画です。
2013年5月3日 10:18 AM |
カテゴリー:洋館造りの古民家 VOL.2 |
コメント(0)
3月27日着工で岩倉の古民家のリフォーム工事が始まりました!!
小学校に入る前のまだ幼く、チャーミングでお茶目な三姉妹のお子様のいらっしゃるお若いご夫妻が施主様です。
築40年ほどということもあり(それほど古くないという意味です!!)、今まで弊社で施工してきた町家のイメージとは少し雰囲気が違います。
初めて拝見した時、いつも通りの町家のイメージでの改装よりも、明治期から昭和初期に建築され京都にもまだ多く残っている和洋館(私の造語?!:和の部材が使われた洋館)のように改装をしたほうが、この古民家をより生かすことができるのではないかと感じました。
また施主様は、ヨーロッパでの海外生活の経験もあり、お持ちの家具や照明もこのご提案のほうがぴったりのようです。
建具は、無垢材の輸入建具を使い、フローリングももちろん無垢材。
壁面はクロスを施工してその上からペンキ塗りの仕様です。
そしてその塗装工事は、なんと!?施主様の施工。
2階部分の2部屋も、窓取替など難しい工事は弊社施工ですが、壁面の塗り壁は、施主様の施工となります。
新しい取り組みが目白押しの今回の工事。
施主様も私達もワクワク!!ドキドキ!!です。
以下は、工事前の写真です。
前面道路側には生垣があり、形の良い三角の屋根にはいぶしの日本瓦が施工されています。
南面の大きな庭には、緑がいっぱいです。
これからこの家に長く住まわれる施主様ご家族のために、最大限できる限りの努力をしていく覚悟で臨んでまいります。
工事については、夏までの長いお付き合いとなります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
Blogged by 松山 一磨(いつま)

(before)建物前面道路側。間口いっぱいに生垣があります。

(before)2つの三角屋根が特徴の古民家。 屋根にはいぶしの日本瓦が施工されています。

(before)玄関です。この角度の形、とっても男前ですね!!

(before)前面道路の生垣の裏側。 ここに駐車場を造る計画です。
次の写真は、既存のウッドデッキです。
腐食が激しいので撤去して、大型の木製ウッドデッキを造ります。
またウッドデッキの向こう側に庭へ突き出したリビングスペースを増築します。
緑をいっぱい感じられる空間です!!
新たに造られるウッドデッキを通って、洋室と増築されるリビングスペースを行き来できるようにする計画です。

(before)腐食したウッドデッキ

(before)既存の2階バルコニー。リフォームして残します!! 手前は、柿木です。

(before)道路側に面した工事前のキッチンと洗面、浴室入口です。

(before)DKから南面庭に面した和室です。 次はLDK横の洋室となる計画です。

(before)上の和室横にある洋室。庭側に増築してここにLDKを配置します。

(before)DKから見た玄関。 右側は階段です。

(before)緩やかでしっかりした階段です。 この階段は再利用します。

(before)WC、新たにリフォームします。

(before)窓は弊社で交換。 壁塗り工事は施主ご主人様の施工となります!! ☆乞うご期待!!

(before)2階和室の天井です。 古さがかえって趣(おもむき)を醸(かも)し出しています。 良い材料だからの結果です。

(before)今はもう生産されていないガラスです。 とっても可愛いデザインですね!!
8:27 AM |
カテゴリー:洋館造りの古民家 VOL.1 |
コメント(0)
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
建築こぼれ話 -その1-
「歌舞伎門(かぶきもん)ってなあに?」
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
今回のブログにでてきましたが、
そもそも歌舞伎門(かぶきもん)とは、どんな門でしょう?
なぜ歌舞伎なのか、起源を調べてみますと…、
昭和時代にできたお洒落な門の呼び方、でした。
歌舞伎の舞台で、役者が出てくるような立派なお屋敷の門に
なぞらえた言葉のようです。
古建築学には、同じ読みの『冠木門(かぶきもん)』があります。
冠木(かぶき)とは、2本の柱の上に1本の横木を渡し、柱を貫通
させた形をいいます。「井」の字の上半分と似ています。
かつては神社や武家屋敷の勝手口によく見られたそうで、
さらに上に屋根をとりつけることもありました。
それが明治時代ごろより習慣が変わり、屋根無しの場合のみを
指すようになったそうです。

古建築の学術的な「冠木門」
ですから学術的には、冠木の形では無く屋根瓦がのった
今回の門は、『数奇屋門(すきやもん)』といえますでしょうか。
お屋敷や茶室の主人が、お客様をお迎えするために自由に
趣向を凝らした門は、『数奇屋門』と呼ばれています。
門と塀だけなのに、奥が深く底が知れません。
構造にも、知恵と工夫があります。
強い風で、カサが飛ばされたことがありませんか?
屋根も、上向きの風を受けているそうです。

吹きとばされるカサ、とばされそうな門
そのため、昔から、門と塀を建てる際には、
屋根が飛ばないよう、各木部は慎重に加工して組み合わせられ、
倒れないよう、門と塀を「コ」の字に配置して踏ん張れるようにし、
土台が腐らないよう、土中には砂利を入れ、基礎の石を重ねて
水はけを良くしてから、門柱を立てていました。
約100年前の門が保たれているのは、それ以前に編み出された
このような知恵と工夫とがあったからなのです。
おつきあいいただき、ありがとうございました。
Blogged by 小川 還
2013年4月7日 8:17 PM |
カテゴリー:2013年4月7日 |
コメント(0)
« 前のページ
次のページ »