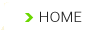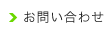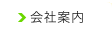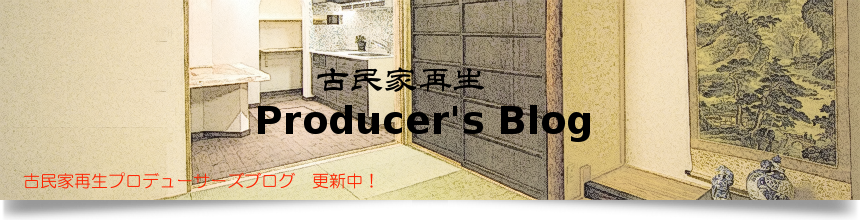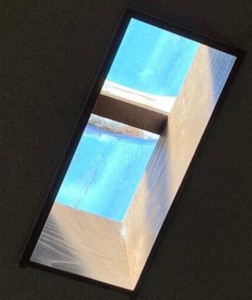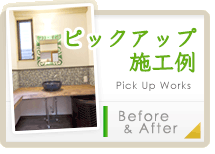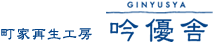『 最近の記事 』
事務所前の紫陽花の続報です。
花が更に大きくなり、色付いてきました。
手前の本紫陽花は、綺麗な桃色です。



西洋紫陽花『アナベル』も緑色から真っ白な花へ変化してきました。
紫陽花は梅雨にふさわしい可憐な花を咲かせてくれます。
暑い夏の前の穏やかな気候を演出してくれる美しい花として、日本ではとても人気のある樹木の一つでもあります。
2種類の紫陽花の間に有る小さな白い花は、山から飛んできたか、鳥に運ばれて来て自生した樹木です。
調べてみましたが、何の花か分かりません。
実ができたら、それを手がかりにまた調べてみたいと思います。
どなたかお分かりの方がいらっしゃり、ご一報頂けると幸いです。


blogged by 松山一磨 & 掛水梨華
2021年6月21日 3:11 PM |
カテゴリー:( 1. お知らせ ) |
コメント(0)
事務所の紫陽花が咲き始めました。
昨年5月に植栽したものです。


手前はお馴染みの『ホンアジサイ』、奥は西洋紫陽花で白い可憐な花を咲かせてくれる『アナベル』です。
北白川でも、少し山手に上がった所に在る事務所。
街中より少し気温が低いように思いますが、その分、植物の開花も少しずれて始まります。
紫陽花は6月中にその花を人為的に切り落とさないと翌年に花を付けてくれません。
また暑い時期にはしっかり水をやらないと直ぐに萎れてしまいます。
世話をするときっちり反応してくれる『お世話しがいのある花』でもあります。


blogged by 松山一磨 & 曽和理恵
2021年6月3日 8:38 PM |
カテゴリー:( 1. お知らせ ) |
コメント(0)


工事の御見積依頼をいただき、本日岩倉へ二人で現調(現場調査)に赴きました。
一旦寒さが和らいだのも束の間、とても寒い朝です。
岩倉でも岩倉西河原町というこの辺りは、山や川の自然と古い農家屋や民家屋が残る
言うならば、日本の原風景をまだ残す地域です。


訪れたお宅のお向かいに有った蔵。
手直しはされていますが、戦前(80年以上前)の建築だと思います。
綺麗に漆喰で造作された窓を見つけました。

桔梗をイメージしたものかもしれませんね。
バランスの良い、美しいデザインです。
この窓は、空気を取り入れるためのいわば『通気口』です。
通気口なので、丸い穴が有ればそれで用は足りるわけです。
それにも関わらず、何故こんなに手間のかかるものを作るのでしょうか?
美しいものは、作った自分のみならず、それを見た人をも楽しませてくれます。
時として感動することもあるのではないでしょうか。
必要なものだけを効率良く作る。
そんな仕事もあるのですが、『造形美』という言葉が著すように、作る物の姿形(すがたかたち)というものに心を込めることもまた大切な仕事だと思います。
京都には、そんな文化が永く息づいていて、そのようにして造られたものをこの町の至る所で見ることの出来る、貴重な場所のように思います。
blogged by 松山一磨 & 曽和理恵
2021年2月4日 10:17 AM |
カテゴリー:( 1. お知らせ ) |
コメント(0)
遂に完成です。
今あるもの、古い建具や階段、手摺り、床板、天窓など、使えるものを可能な限り再利用した工事です。
これから力を合わせて人生を切り拓いて行く若いご夫婦。
無理をせず、可能な予算内でプラン作成をさせて頂きました。
・水回りは西側一直接に配置
・部屋を一つ解体して造った広いリビング
・吹き抜けの高い勾配天井
・限られたスペースいっぱいに製作した造り付けの浴室
・リビングに隣接した庭が見える大きな窓
・タイル貼りパーテーションの対面キッチン
・タイルと信楽陶器で造った洗面台
主だったご要望は概ね実現出来たようです。





外観は次の課題として、既存の状態としました。
ただし、窓に障子を新設しました。
内外両方で町家らしい雰囲気を醸し出してくれます。
外灯、玄関ホールの照明はレトロ感溢れるものをご提案しました。
古い造りのこの家に馴染んでいるように思います。




古い建具を綺麗にリフォームして再利用しました。
新しい建具では表現出来ない懐かしくも重厚な雰囲気があります。



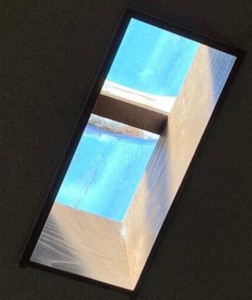
吹き抜けの高い勾配天井。
大きな梁や母屋は当初から有るこの家の構造体です。
化粧(磨いて塗装)を施しています。
初めから有る天窓を再利用しています。青い空が見えています。




二階とそこから望む一階リビングです。
階段手摺りは古いものを補強して再利用。
高い位置にある古い壁はそのまま残しています。
往時の雰囲気が伝わる貴重な壁。
*薪で料理をしていたことで壁が黒く煤(すす)けています。









【 キッチン 】
キッチンに隣接したパントリー
棚は可動式で収納するもに合わせて、調整が可能。
キッチン周りの壁は、キッチンパネルでなく、モザイクタイルを採用。
ナチュラルで個性的な仕上がりになります。
【 浴室 】
サイズ、形状共にシステムバスが入らない空間です。
限られたスペースいっぱいに天井も勾配のフリオーダー浴室を造りました。
忙しいお二人のご要望で、タイルや桧でなく、お掃除のし易いパネル仕様で製作した浴槽。
お庭を眺めながら入浴が出来る配置になっています。
【 洗面台 】
タイルと信楽陶器の造作洗面台。
お好みのタイルと信楽陶器シンクを選んで頂きました。
複数回に及ぶ打ち合わせは、ご夫婦として結婚生活初めての大きな共同作業だったのではないでしょうか・・・?
お好みの違いや考え方の違いを一つ一つ乗り越えて完成した家。
センスの良いお二人ですので、家具や家電製品を配置されたら、とても素敵な空間になると思います。
最後になりましたが、長い工事期間を通して、常にご協力的に対応をして頂けましたことに心より深くお礼申し上げます。
blogged by 松山一磨 & 掛水梨華
2021年1月26日 10:15 AM |
カテゴリー:( 1. お知らせ ) |
コメント(0)

お客様各位
協力業者の皆様
新しい年を迎え弊社も通常通りの営業をスタート致しました。
本年も、皆様により一層ご満足頂けるよう、業務に精励いたす所存でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、新型コロナウイルスによる影響で大変な日々が続いておりますが、
この状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、
皆様のご健康をお祈り申し上げます。

株式会社吟優舎 社員一同
2021年1月11日 9:04 AM |
カテゴリー:( 1. お知らせ ) |
コメント(0)
« 前のページ
次のページ »