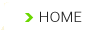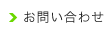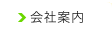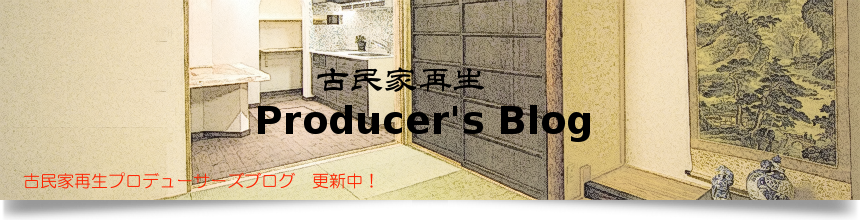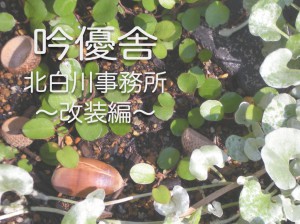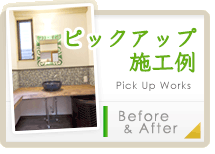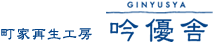『 最近の記事 』
【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】
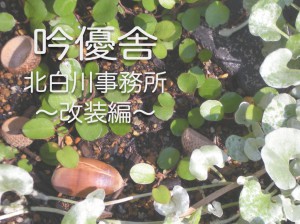
・吟優舎 北白川事務所 改装編 第七弾!
左京区北白川の事務所改装の続報です。
時期外れとなりましたが、Vol.6で消えた壁部の改装、
「暖炉コーナーづくり」をご報告いたします。

(before)北白川事務所 工事前の外観
こちらから以前の状況がご覧いただけます。
(→ Vol.1) (→ Vol.2) (→ Vol.3)
(→ Vol.4) (→ Vol.5) (→ Vol.6)

・事務所内から見たオーダーメイド木製窓
窓台の枠まで木製…という、今となっては珍しく
昔懐かしいオーダーメイドの窓も、弊社にすっかり
馴染んで(なじんで)きたようです。
時折、コトン!カツン!と屋根にあたるどんぐりの音。
まだ冬の半ばの昼下がり、スタッフ一同が集まりました。

(before)塗装前 暖炉コーナー

(before)暖炉コーナー 塗装後
本日まで、コンクリートブロックを組んで積み上げ、
白のモルタル塗装と焦げ茶のタイル貼りで仕上げた
暖炉コーナーの姿です。
工事完了につき、弊社の設計デザイン担当者が
周辺の状況を初めてチェックします。
いかがでしょうか?
皆様も、設計士の目でご覧になってみてください。

(before)東側の壁 左

(before)東側の壁のつづき 右
「この空間は、何かが足りず、寂しいです!」
と、設計デザイン担当者のひと声が。

・暖炉に魔法が必要では!?
すぐさま、追加工事にとりかかりました。

(before)タイル幅などを実測確認

(before)今回選んだ陶器タイル
まるでパウル・クレー(→こちら Paul Klee)の絵のような、
鮮やかで色とりどりの陶器タイルを縦に並べることになり、
まず、タイルを貼る土台となる木部を造作していきます。

(before)タイル貼付け面を造作
同時に、
大工職人の手で、建具の枠を太くし厚みをもたせ、
スイスの古民家のように木部の存在感を際立たせます。

(before)建具枠を重厚に
色調を確かめながら慎重にタイルを貼り進め、
目地材(めじざい)を塗り込み、乾かします。

(before)目地材 乾燥中
数時間後に目地材を拭き取り、本日の工事が完了しました。
皆様、いかがでしょうか?

(本日のafter)暖炉周辺完成
( ↑ 写真をクリックすると大きくなります)
最後に、暖炉に火を入れてみました。
まだ寒かったこの時期、本物の火を見て暖まり、
ほっとするひと時でした。

・暖炉点火
では、次回こそ、完成後のすべてをご披露したいと思います。
おつきあいいただき、ありがとうございました。
Blogged by 小川 還
2014年6月24日 5:24 PM |
カテゴリー:事務所 Vol.7 |
コメント(0)
【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

(after)洋のリビング ・吹き抜け
杉皮塀のある町家、完成編【 後半 】をお届けいたします。
※過去ブログへ → VOL.1・ VOL.2・VOL.3・ VOL.4・ VOL.5)
写真は、キッチンから見た洋のリビング。

(after)玄関内周り
天井を撤去し、屋根に天窓を造作しました。
吹き抜けにすることで、大きな梁や柱、勾配の屋根裏が見え、
変化に富んだ空間が創り出されました。
そして天窓からの光がさらにその変化に彩(いろどり)を添えてくれます。
このお屋敷ならではの美しさが際だったように思われます。

(after)吹き抜け 〜02〜
夕暮れの陽光が、天窓から吹き抜けへ差し込み、
様々な梁影を映し出し、退屈しません。
ちなみに上部の丸太の梁は、以前から有った古いもの。
下に見える角材の梁は、デザインと補強を兼ねて造作した新しいものです。
見た目には、どちらも元々有った古い梁に見えますが・・・。

(after)両開き窓を引戸に改造
リビングスペースの両開き窓は、
新しく外格子を取付け、そのまま引戸にリフォームしました!!
既存の開き窓の建具に溝加工を施し、納めています。

(after)アンティーク戸
室内各所に大正から昭和初期製造のアンティーク扉を設(しつら)えました。
扉の向こうは、和のリビングスペースです。

(after)和のリビングスペース
変色がなく、肌触りの優しい和紙の市松畳
オリジナルの京唐紙(からかみ)
新規造作のコンパクトでかわいい書院
個性豊かな和のリビングスペースの完成です。

(after)隠れ家的な書斎
押入の隣には、奥様の強いご要望であったミニマムな書院が完成しました!!
幼いお子様の様子を見ながらササッとメールを書いたり、本を読んだりと・・・
隠れ家のような空間で、作業にも集中できそうです。

(after)京唐紙(からかみ)の襖
襖(ふすま)は、伝統ある京唐紙(からかみ)へ貼り変えました。
柄(がら)はもちろん、紙色、紙質まで選んで、昔ながらの版木を使っての職人の手で作られる京唐紙です。
一点しか存在しない本物の逸品です!!

(after)新しい階段
さあ、二階へどうぞ。
階段は傾斜を緩(ゆる)くし、お子様が登りやすいように
段数を増やしています。
手摺(てすり)も大工造作で製作したオリジナルです。

(after)2階の洗面 〜01〜
町家イメージの洗面台の完成です!!
右のアンティーク戸(二階トイレ入口)とのバランスを考え、
この家の風格に合う、”渋さ”のあるデザインに。
陶器製の洗面ボウルが載(の)る天板は、一見(いっけん)、木の板に見えますが、
水の変色や腐れを考慮して、木肌色の陶器タイルを採用しています。

(after)2階の洗面 〜02〜

(after)2階の洗面 〜03〜
照明・鏡・陶器製洗面ボール・タイルなどは、
『 大正期の町家の 趣(おもむ)き 』を表現するように、
設計デザイン担当者が現場で実際の色や風合いを確認して選んだものです。

(after)和室の押入棚
一階和室の押入。
ここは二つあった階段の一つを撤去して収納にリフォームしたもの。
施主様のご要望をお聞きして、従来の中段のみの押入でなく、
洋服ダンス代わりにも使えるように
可動式の棚やネクタイハンガー、ズボンハンガー、パイプハンガーを設置しました。

(after)ウッドデッキバルコニー 〜01〜
一階キッチンの屋根上に空中庭園さながら!? 広いウッドデッキバルコニーを新設しました!!
正面にある目隠しの塀は、手前と奥に縦板を交互に並べて造作した
菖蒲張り(あやめばり)という和の木工仕上げです。
視線を遮(さえぎ)り、風を通します。

(after)ウッドデッキバルコニー 〜02〜
お子様が簡易プールに入って遊んだり、
外でちょっとした軽食をとったりできるように、
ここにもかわいいタイル仕上げの手洗い場を設置しました。
さて、最後のお掃除が済み、メンテナンスの日まで、
私達スタッフはこの家とお別れです!
築80年以上の風雅なお屋敷。
この家を引つ継がれた若きオーナー様のセンスと往時の細やかな
彫刻や加工が施された素敵なデザインのコラボレーション(融合)。
新たな80年間を超えて、また次に受け継がれていくことだと思います。
弊社の建築とデザインは、完全な復元ではありません。
残すべき良きものは残し、新しい部材が馴染むよう、
設計デザイン担当者と職人が奮闘した結果が、こちらのお屋敷です。
いかがでしょうか?
最後になりましたが、
ご信頼いただき、その多くを私たちにお任せくださった施主様に
心から深く、お礼を申し上げます。
誠に有り難うございました。
こちらの『杉皮塀のある町家』 は、弊社のホームページの
『 ピックアップ施工事例 Before&After 』にて、工事前と完成の様子を
詳しく確認することが可能です。
よろしければ、合わせてご覧ください。
『 ピックアップ施工例 』
(→ コチラ http://www.ginyusya.com/pickup/detail_08.html)
おつきあいいただき、ありがとうございました。
Blogged by 小川 還
( 監修 : 松山 一磨)
2014年3月16日 10:53 AM |
カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.6 |
コメント(0)
【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

(after)門周辺 〜01〜
杉皮塀のある町家、ついに完成編、前半をお届けします!!
(※過去ブログはコチラ→ VOL.1・ VOL.2・VOL.3・ VOL.4)
では、お邪魔いたします! m(_ _)m

(after)門周辺 〜02〜
最初の改修は、傷んだ歌舞伎門と杉皮塀からスタート。
左は従来の塀、右は弊社にて新しく造作した塀です。

(after)左/門から、右/玄関前から
背の高さで両側に濃い色があると圧迫感があるため、
設計デザイン担当者のアイデアで、
杉皮塀の一部を、白い漆喰壁にしました。
下部も従来より高めの位置で杉皮をカット。
結果的に、水仕舞いも良好に。

(after)玄関周り 〜01〜
左手の表玄関は格式ある昔のスタイルのままで残し、
右手の裏玄関を通常使う玄関として、リフォームしました。

(after)玄関周り 〜02〜
玄関を一歩入ると…

(after)裏玄関 兼 勝手口の天井
照明のアンティーク風ガラスシェードから反射し、
光の断片があちこちに漂います。

(after)玄関土間のモザイクタイル完成

(after)モザイクタイルのアップ
足元の土間には、カラフルな陶器製モザイクタイルを
埋め込みました。

(after)玄関内部
広い式台の上に、大容量の下駄箱をオーダーメイドし、
室内との境にはアンティーク戸を設置。
式台のフローリングは、フランス製の松材で波型加工された珍しいもの。

(after)玄関から見る
町家独特の天井の低さを解消するため、
玄関ホールから室内に入ってすぐのところに位置するリビングの天井を吹きぬけにしています。
見えている建具はすべて、大正から昭和初期に製作されたアンティーク建具を再利用したものです。
ちなみに左手のガラス戸は、この家の二階に有ったものを移動し、再利用しています。

(after)アンティーク照明
室内や廊下、トイレにも、アンティークをイメージした照明を
ふんだんに取り入れました。

(after)キッチン 〜01〜
リビングの隣は、ダイニングキッチン。
既存のシステムキッチンの収納部をリフォームし、
木目調に。
取手はすべてメタル製取手にリメイクしました。
壁面にはレトロイメージの陶器製モザイクタイルを施工しました。

(after)キッチン 〜02〜
中央にあるステンレス天板のキッチンカウンターは、
弊社のオーダーメイドで造作したもの。
左の大きなアンティークガラスの飾り窓からは、
玄関からの出入りはもちろん、
リビングにいる家族の気配を感じられ、
反対側のご家族もキッチン内の様子を知ることができます。

(after)キッチン 〜03〜
カウンターは、リビングからのお客様の視線を隠す
衝立(ついたて)でもあります。
背面の棚には、炊飯器や魔法瓶等を収納できるよう
にスライド棚を2カ所もうけ、コンセントを設置。
パンをこねたり、軽食をとったり、料理本を開いたり…
毎日楽しみながら使っていただいているご様子です。
さて、次回ブログでは、吹きぬけのリビングへ戻り、先をご案内いたします。
続編の「完成編!後半」 お楽しみに!!
弊社では、経験をつんだ設計デザイン担当者が改装中に
現場での造作の仕上がりをチェックし、吟味します。
そのたびに、色彩と空間とお客様がご要望されている
インテリアのイメージを再検討し、
ベストな状態へと修正する体制です。
完成編!後半でも、これまでご案内した工事中の風景が
どのように変化してくか、ご確認していただけます。
こちらの『杉皮塀のある町家』 は、弊社のホームページの
『ピックアップ施工事例』で ’ before & after ‘ を比較した
写真記事としてまとめてあります。
合わせてご覧ください。
「ピックアップ施工例」
(→ コチラ http://www.ginyusya.com/pickup/detail_08.html)
おつきあいいただき、ありがとうございました。
Blogged by 小川 還
( 監修 : 松山 一磨)
2014年3月2日 1:03 PM |
カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.5 |
コメント(0)
【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

(after)外観 〜01〜
比叡山が見える家、ラスト「完成編」をお届けいたします!
(※過去ブログへ→ VOL.1・.2・.3・.4・.5・.6・.7)

(after)メタル製 窓格子
外構完成後、家正面の窓にメタル製の格子を設置。
各窓ごとにサイズを調整し、オーダー製作しています。
玄関までのアプローチも出来上がりました!!

photo 岩倉、アプローチ 01

(after)アプローチ 〜02〜

(after)アプローチ 〜03〜
とうとう、『洋館造りの古民家』が完成いたしました!

(after)外観 〜02〜
ピンポーン♪~♪
撮影にうかがいました!
では、皆様とご一緒に、お邪魔いたしましょう!! カチャッ…

(after)玄関内部
お施主様がフランスのノミの市で見つけてこられた
素敵なアンティーク照明が取付けられ…

(after)玄関周辺
同行したカメラマンがこの光景に思わず、パシャリ。

(after)セカンド洗面台 〜01〜
フランス製の石けんや、おしぼりのようにセットされた台拭き。

(after)セカンド洗面台 〜02〜
奥様の手でセンス良く美しく飾られた洗面台に、
スタッフ一同がうっとり・・しました。

(after)セカンド洗面台 〜03〜
この手洗いスペースは、ユーティリティ(脱衣洗面室)へと繋(つな)がっています。
そしてそのユーティリティは、さらにリビングスペースへも繋(つな)がっています。
さて、ここで時間を巻き戻し、家引き渡し前のリビングへ。

(after)リビング 〜01〜
右側は、キッチンスペース。左側は、ガーデンスペースです。
正面の窓下には、木製の小さなデスク、お子様たちの勉強机!?を造りました。

(after)キッチン
キッチンからは、リビング~庭~隣接の洋室までをぐるりと
見渡せ、まだ小さな3人のお子様のようすが確認出来るように設計されています。

(after)リビング 〜02〜
庭に張り出すように増築されたリビングスペース。
緑豊かな庭に、リビングと隣接の洋室の2つのテラス窓をつなぐ広いウッドデッキを造作しました。

(after)洋室&リビングとウッドデッキ
バーベキューをしたり、子供用プールを置いて楽しんだり、
疲れた時の気分転換もできる庭に生まれ変わりました。

(after)洋室から庭を見る
窓を開け放てば、屋外まで1つの空間として楽しめます。

(after)庭から見たLDK
ではラストです!
ご主人と奥様が協力して塗装された(壁、床、柱、窓周りなど木部)
邸内の仕上がりをご覧ください。
お施主様ご家族の皆様、
お忙しい中にもかかわらず、撮影をご快諾いただき、
本当にありがとうございました。 m(_ _)m
こちらの「before&after」の様子を弊社ホームページの
ピックアップ施工例で詳しくご覧いただけます。
※「ピックアップ施工例」
(→ コチラ http://www.ginyusya.com/pickup/detail_09.html)
本日はおつきあいいただき、ありがとうございました。
Blogged by 小川 還
( 監修 : 松山 一磨)
12:08 PM |
カテゴリー:洋館造りの古民家 VOL.8 |
コメント(0)
【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

(afterの一歩手前)外観
お待たせいたしました。 m(_ _)m
比叡山が見える岩倉の家、続編です。
前回までで(※過去ブログへ→ VOL.1・.2・.3・.4・.5・.6 )
木工事と塗装までの完了をご案内しましたので、
今回は、タイル貼りと外構の仕上げをメインにお届けいたします。
では、まずタイル施工の様子から・・・
急な来客時にも気軽にお使いいただける、
お洒落な「セカンド洗面台」へどうぞ。

(タイル乾燥中)セカンド洗面台 〜01〜

(タイル乾燥中)セカンド洗面台 〜02〜
厚みのある台座ベースの一枚板を曲線にカットし、
タイルは、ピアノのカーブをイメージした白い鍵盤のような
細長い陶器製を採用しました。
壁面には、光の反射がきれいなガラス製の
黄系混色タイルを貼っています。

(after)ユーティリティの洗面台
ユーティリティーの洗面台にも同じタイルを施工。
こちらはデザインというよりは、壁面汚れ防止のためのもの。
洗面台横のクロスが汚れるのは、嫌なものですね!!

(タイル施工中)キッチン周り
さて、次はキッチンです!
こちらは青のモザイクタイルで統一しました。
カウンターと右壁面、奥にあるシェルフをご覧ください。
茶色い裏紙がずらりと並ぶ部分が、タイル施工箇所です。
カウンター正面の棚内部のみ、裏紙を剥がし終わりました。

(タイル施工中)シェルフのアップ
シェルフは、お施主様のお持ちの家電器具に寸法を合わせて棚を造る、
オーダーメイドの設計です。

(タイル施工中)シェルフ背面のタイル
小さなモザイクタイルは、工場出荷時に約30センチ角の茶色い裏紙に
並べて貼られており、それをそのまま壁に接着します。
水で濡らすと裏紙がスルリと剥がれ、ピカピカのタイルが顔を出しました!!

(タイル施工中)カウンター棚内部のアップ
タイル職人がひとつずつまっすぐに角度を整えていきます。
目地入れを済ませ、水拭きし、表面を磨けば仕上りです!

(タイル施工中)玄関&ポーチ
次は、玄関ポーチへどうぞ。
特大の陶器タイルを使います。
約40センチ角もあり、ちょっとした歪みが目につくため、
現場にて、タイル職人と細かい寸法を打ち合わせします。
設計デザイン担当者が職人を前に考え込む、緊張の一瞬!
「 タイルの隙間は2ミリ。切断はこの角にそってください (>人<;) 」
こうして、施工がスタートしました。
もちろん、玄関の外でも、作業が進んでいきます。

(外構施行中)アプローチとカーポートの造作
家の正面では、門から玄関へのアプローチ造りが進行中。
大きな飛び石は、互いに平行に並べて洋館らしさを演出します。
隣では、左官職人がカーポートを施行中です。

(外構施行中)カーポートの洗い出し
表面仕上げは、オレンジ混色の種石を使った
洗い出しの円形のグラデーション。
滑り止めと飾りを兼ねた、かなり珍しい仕上げです。
乾燥後にモルタル表面を水で洗い流し、種石を浮き出させる
ことから「洗い出し」と呼ばれます。
足場無しで、職人が板きれに乗って板の跡を消しつつ進むという、
なかなか体勢のきつい作業です。
「外構」とは、「外部を取り巻く構造物」です。
家の外にある、塀・カーポート・植栽などを全部まとめたもの。
日本では、高い塀で外から隠し、庭はすべて邸内の延長として
楽しんできたせいでしょうか!?
英語の「エクステリア exterior(外部装飾)」は、
「インテリア interior (室内装飾)」とペアですが、
「内構」という言葉は使いませんね・・・・(^。^)

(before)ウッドデッキ施工準備中
庭では足場が片付き、ウッドデッキの造作開始。
いよいよ最終段階です。
次回は、完成編です。
完成したアプローチを中心に、
家全体をご案内していきます。
おつきあいいただき、ありがとうございました。
Blogged by 小川 還
( 監修 : 松山 一磨)
2014年3月1日 7:39 PM |
カテゴリー:洋館造りの古民家 VOL.7 |
コメント(0)
« 前のページ
次のページ »